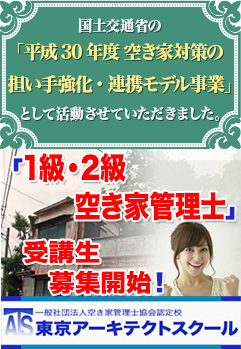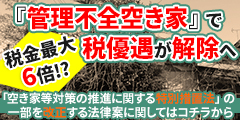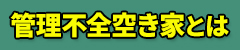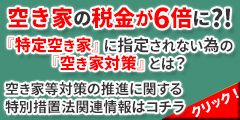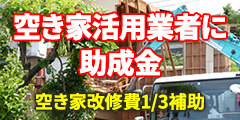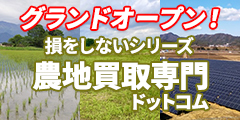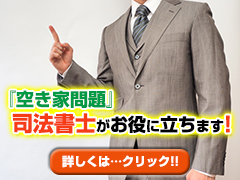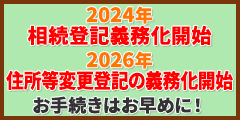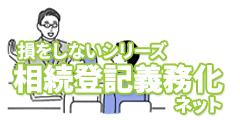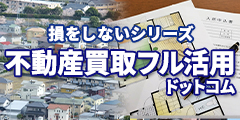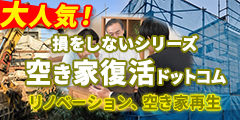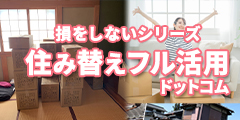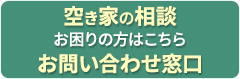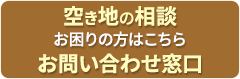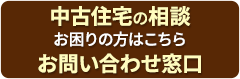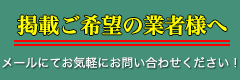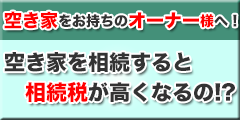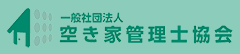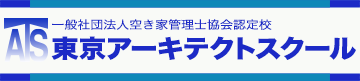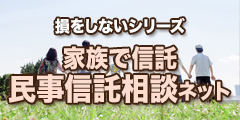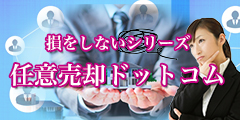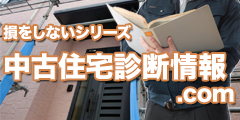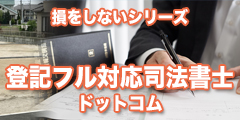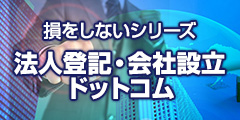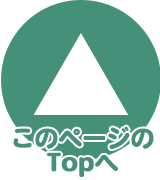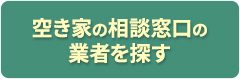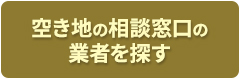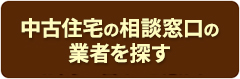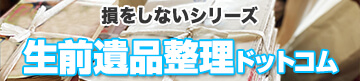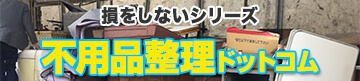相続空き家、有利に売却 共有なら控除拡大 (日本経済新聞)
- 2016/12/07
相続した空き家と土地を売ると譲渡所得3000万円まで税金がかからない特別控除制度。4月に始まり、控除枠の大きさから関心を持つ人は多いだろう。しかし売却期限など様々な条件があり、共有で相続すると控除総額が増えるという利点もある。制度をよく知り、円滑な売却に役立てよう。
「譲渡所得の節税メリットは大きい」。税理士法人、山田&パートナーズの浅川典子税理士はこう話す。譲渡所得は売却価格から家屋・土地の取得費用と、家屋の取り壊し費用など譲渡費用を差し引いて算出する。税率は約20%なので3000万円の特別控除が適用されれば、最大約600万円の節税になる。
■売却時期に注意
それだけに関心は高く、浅川氏のもとには顧客から相続の相談を受けた銀行の担当者が問い合わせてくるようになったという。制度開始から日が浅いとあって誤解も目立ち「例えば古い家ならすべて対象になると思われているようだ」(浅川氏)。
まず知っておきたいのは特例の対象が2013年1月2日以降に発生した相続であること(図A)。さらに相続が発生してから3年後の年末までに売らなければならず、売却は特例の実施期間内(16年4月1日~19年12月31日)にすることが必要だ。
例えば13年3月に相続した人は、16年4月1日から12月31日までに売却すれば対象になる。これより前に売っていても遡及適用はされない。特例が適用される期間は相続発生時期によって異なり、14年に相続した人は16年4月から17年末までだ。今年1月に相続した人は4月から制度の終わる19年末までとなる。
空き家の定義にも条件がある。まず、亡くなった人(被相続人)が一人暮らしをしていたこと。老人ホームに入居し住民票も移していた場合は、空き家で相続しても特例の対象にならない。空いている部屋に賃借人を住まわせていた場合も対象外だ(表B)。
空き家が建てられたのが1981年5月以前であることも条件だ。ただし同年6月から建物の耐震基準が変わったため、売却する場合は新基準を満たすリフォームをする必要がある。不動産業者に売却する際、古い家をそのまま土地とともに売りがちなので注意しよう。リフォームをしないなら、空き家を取り壊して更地にしておかないと特例の対象にならない。
一般的に複数の相続人が不動産を相続する場合、共有名義は避けるのが無難とされる。売却価格や時期などを巡って意見が食い違い、トラブルになりやすいためだ。しかし今回の特例は共有名義で相続してから売却すると、相続人それぞれが3000万円の特別控除を受けられる(図C)。兄弟2人で共有名義にすれば、相続人全体で使える特別控除の額は6000万円と2倍になる。もし3人なら9000万円になる計算だ。
ただし特例を受けるためには、相続人全員が建物と土地の両方を相続することが必要だ。例えば母親が亡くなって兄弟2人が相続する際、土地は2人で分けたのに家屋は兄の名義にすることがありがちだ。しかし「これだと特例を受けられるのは兄だけになる。家屋・土地とも2人の名義にしておきたい」と東京シティ税理士事務所の石井力税理士は助言する。
■更地の写真も提出
家屋を取り壊して更地を売却する場合も注意点がある。それぞれが相続した土地を売る時期は異なっても構わないが、兄が売却した3年後の年末までに弟が売って売却価格の合計が1億円を超える場合「兄弟とも控除の対象外になる」と安心資産税会計の高橋安志税理士は指摘する。
売却してからの手続きも知っておこう。特例を受けるには売却の翌年に確定申告する。その際、空き家だったことを所在地の市区町村長に証明してもらう書類「被相続人居住家屋等確認書」を付ける必要がある。
市区町村長への申請には、被相続人の除票住民票、土地建物の売買契約書、電気ガスの閉栓証明書などがいる。家屋を取り壊して更地で売却する場合は、空き家があるときの写真と取り壊し後の更地の写真も提出する。相続が発生してから土地を貸したり、事業をしたりしていないことを証明するためだ。
譲渡所得の計算では家屋と土地の取得費が必要になる。購入したときの売買契約書があればいいが、古い物件では見当たらないこともあるだろう。「特に先祖代々受け継いできたような土地の取得価格は分からないことが多い」(辻・本郷税理士法人の松浦真義税理士)。その場合は売却価格の5%を取得費として計算するのが基本だ。
土地については日本不動産研究所が算出する市街地価格指数を基に推計する方法もある。取得費の5%で計算する場合と比べてどちらが有利かを税理士など専門家に相談するのも選択肢だ。(川鍋直彦)
■小規模宅地の特例 併用できる場合も
亡くなった親が住んでいた自宅を相続する場合、相続税の負担を軽減するため敷地の評価額を8割減らせる「小規模宅地等の特例」を使いたい人は多いだろう。この特例は被相続人と同居し、相続後も住み続けることが条件の一つなので、今回のような相続空き家を売却するケースでは使えないことが多い。
ただし同居していなくても、相続人が相続開始の直前3年間に賃貸住宅に住んでいたなどの条件を満たせば、小規模宅地等の特例が適用される。このため、相続した敷地を相続税の申告期限まで所有し続け、相続が発生してから3年後の年末までに売却すれば、両方の特例を利用できる。
[日本経済新聞朝刊2016年10月26日付]